
自治体発行の「米にも使える」クーポンがばらまかれそう。「現金給付より支出促す効果“倍”」。
政府が近く取りまとめる総合経済対策の概要では、米にも使える食料品クーポンが
主力となりそうです。
政府関係者によると、経済対策の概要では、物価高対策として、自治体が自由に使える「重点支援地方交付金」を拡充し、食料品の購入などを支援するとしています。
具体的には、コメを含めた食料品全般で使えるクーポンの発行などを自治体に推奨する考えです。
(中略)
こういった「プレミアム付き商品券」や「クーポン」はどういった効果があるのでしょうか。
第一生命経済研究所の永濱利廣首席エコノミストは「現金給付だと経費や手間がかかるけれども、プレミアム付き商品券などはすでに行っているので、自治体はスムーズに進められて、現金給付よりも支出を促す効果が倍近くあるのでは」と指摘。
そして、「物価高対策としては、いかに安く買ってもらうかが重要」ということで、「商品券だと貯蓄に回らずにお得に買い物ができるので効果が大きいだろう」といいます。
一方で、「プレミアム率などは地方任せになってくるので、格差はある程度仕方がないのでは」ということでした。
【解説】政府の総合経済対策“クーポン発行”は「現金給付より支出促す効果“倍”」経済専門家が見解 プレミアム率などで地域格差も「地方任せなので仕方ない」(FNNプライムオンライン(フジテレビ系)) – Yahoo!ニュース
1999年には地域振興券というものがあって、1人2万円ずつ配られましたね。
あれどうなったんだろう。当時の公明党が要求して小渕内閣が配ってたみたい。使った記憶があまりないのですが。
地域振興券 – Wikipedia
確かに現金で2万円などを貰っても、多くの家庭では「ほーん、これっぽっちを単発で貰ってもな、
貯金しとこ」となって終わりでしょう。2万円を真剣にありがたがる層はもう家計が破綻しているので、
早く行政の支援を受けたほうがいいです。
これが10万円消費まで20%還元、最大2万円還元、期間は来年いっぱいまで、などの施策があるならば、
じゃあ使わないと損だよね、ということで消費が喚起されます。
一過性の経済政策にはなりますが、果たしてそれは持続可能かどうか。本当に困っている層に届くかどうか。
クーポンやポイントを配るにしても、すでに地域ペイや地域クーポンがあったり、PayPay提携済みの自治体と、
それらのノウハウがない自治体では、発行も管理もコストが異なってくるでしょう。
それらは還元率に反映され、自治体ごとに差が出るでしょうね。
まぁ自治体ごとに補助金やらで差があるので、今更そこに文句を言っても始まりませんが。
インフラが滅びる地域、熊に侵攻されて外出すら出来ない地域がある一方で、東京都の一等地のように
公立学校で修学旅行先が海外、という地域もありますから。
そもそも消費が増えるとインフレ圧が高まるのですが、それはいいのでしょうか。
果たして経済政策、どうすべきが正解なのやら。








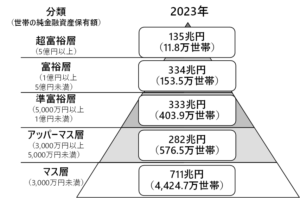





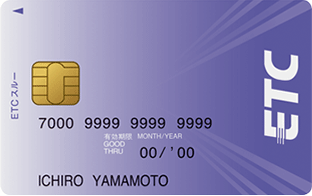



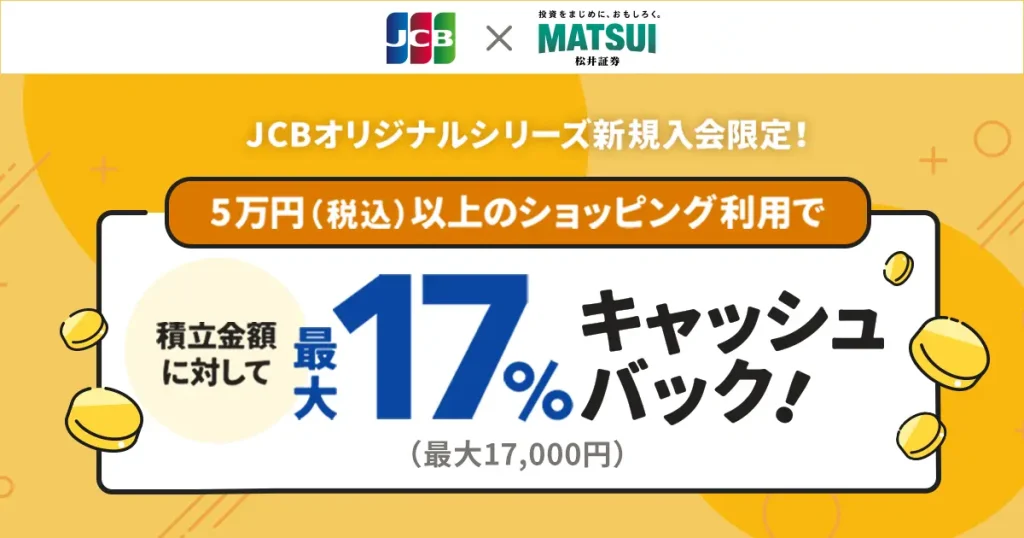


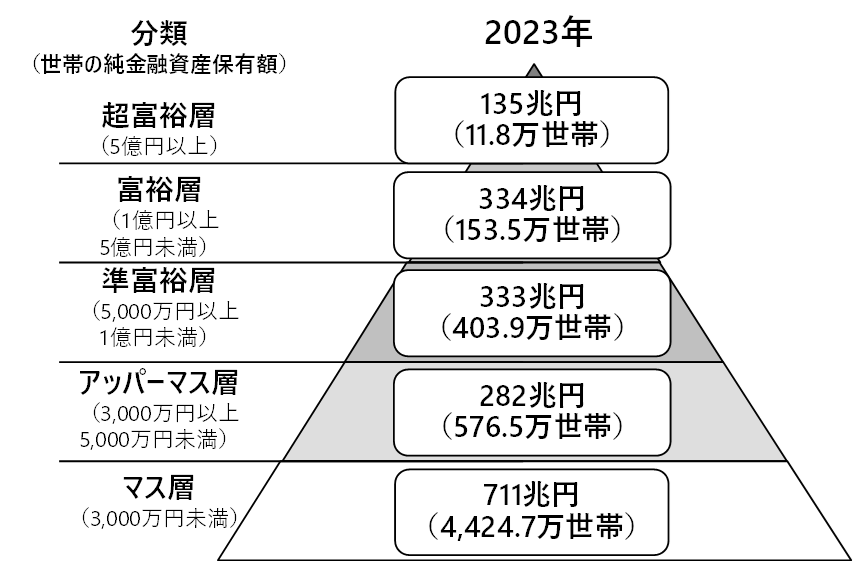






対象限定なしなら高いコメなんかで使わないけど、「コメを含めた」「コメにも使える」って農林族対策のゴリ推しが雑草生える
公立学校海外旅行のエリアのタワーマンションに住んでいますが、東京23区は、税収が余った区は赤字区へ補填しないといけないので、貧乏区にあげるよりは住民への還元をした方がいいので、70万円/人 区が補助になっています。区道も常にきれいだし、税金の無駄遣い万歳!
待て待て
大雑把なツッコミで済まないけど
東京都特別区の場合
税プール制を採用している為か44.9%東京都側の収入 残りの55.1%は住民数に応じて 23特別区に割り振られた交付金が決まる仕組みだった筈
区民の民度が低いと 区長や区議会議員等の特別職の報酬が高く 多選の割合が高い
ちゃんとフードスタンプ導入して欲しいな。
でナマポとかにも適用すればいい。
何なら年金も一人あたり1~2万円分はフードスタンプで支給すればいい。
汚職事件・・・ぢゃなかった
お食事券にすればいいのに。
お茶漬け吹いた
現金なんてパチンコに使うか貯蓄に回るだけ
貧困は貯金ができないから貧困
経費が掛かろうが愚かな貧困のためには限定クーポンしかない
思い出せばコロナの時の特別定額給付金も同じような末路だったような
投資の才能もセンスも無い底辺雑魚ワイはアップルの株を買ったけどエヌビにしときゃよかったと未だに後悔してるから投信積み立てやってる
何も配らないで消費税廃止がいちばんや
代わりに金融所得課税、不動産取得税と所得税を上げればいいだろう
あとは宗教法人にも課税やね
金持ちトンズラで皆貧乏になる奴や
宗教法人に課税って日本を新興宗教だけにしたいのか・・?
1000歩譲って金融所得課税を譲るとしても不動産取得税はどうしてだ?
所得税増税なんて愚の骨頂やぞ
金持ちは株か不動産のどちらかが、大部分締めてるからな。
やっても所得制限かけるだろうし一般庶民には関係ない話
いやいや、一言に不動産って言っても低廉な空き家等があるように、そもそも国が一定規模未満の宅地についてはもっと取引せぃってスタンス
例えばタワマンや一定規模の建物の取引についてだけ増税するにしても免税になる方法を悪用しようとするヤカラが大量発生しても不思議じゃない
なので投機的取引や三為契約については大幅増税するなら納得するけど、取引額や面積要件の寡多のみで単純に不動産取引を増税するのは理解しない
取引額や面積要件については国土利用計画法によって既に法規制が存在するしさ
ああ、消費税しか払ってない人か